【ファン・ドールン】

明治政府は、近代化のための科学・技術習得のため多くの外国人を日本までの旅費支給、無料の官舎、高額の給料で招いた。
運河・干拓・利水・治水については、先進技術国であったオランダから技師を招き「コルネリス・ヨハンネス・ファン・ドールン」もその一人だった。 オランダの技術者で、明治 5 年に来日し、土木寮の長工師という技術者として最高位の職にあった。
ファン・ドールンの指導で、1878年(明治11年)5月、猪苗代湖水の出口だった戸の口十六橋に水位計を設置し、既設利用の必要水量を測定。湖水の出口である日橋川を掘り下げ、水門を設置して利用水深を可能とした。この十六橋水門の完成により、東西の流量調整が可能となり、水害防止を図り、対岸からの安積疏水への取水が可能となった。。
ドールンが、安積疏水開削工事が可能であることを認めたことで、初めての国営による農業水利事業が着工されることになった。
猪苗代湖の十六橋水門脇(会津若松市河東町) に建つドールンの銅像は昭和5年に建立された。安積疏水の設計はドールンであり、安積開拓の父として称える碑文が刻まれている。
この銅像は戦時中、軍事産業の資源として撤去回収され、そのまま砲弾になる運命だった。「恩人の銅像を砲弾にするのは忍びない」と、安積疏水常設委員渡辺信任が、ひそかに山の中に埋め隠し、武器とならずに済んだ。戦後に掘り出され復帰した。銅像の足は台座から外すときに壊したのでセメントで固めてある。このエピソードは「隠されたオランダ人」として全国的な反響を呼び、オランダを感激させるなど国際親善にもつながった。
| 年号(西暦) | できごと |
| 天保8年(1837年) | オランダのヘルデランド州で生まれる |
| 明治5年(1872年) | 明治政府の招聘により来日。利根川、淀川、函館港などの改修・築港に参画 |
| 明治11年(1878年) | 猪苗代湖現地調査 |
| 明治12年(1879年) | 政府に疏水計画を提出 |
| 明治13年(1880年) | オランダに帰国綬賞を贈られる |
| 明治13年(1880年) | 勲四等旭日小綬賞を授与される |
| 明治39年(1906年) | アムステルダム市内の自宅逝去(69才) |
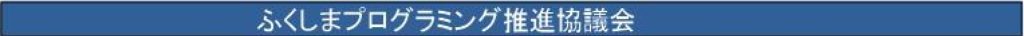

【旧久留米藩士族】 -300x171.jpg)
